往来物造句
- その内容から往来物の祖ともいわれる。
- この「往来物」は、教育に関連した書きかけ項目です。
- この「往来物」は、日本の歴史に関連した書きかけ項目です。
- 江戸時代には、室町期の「節用集」や往来物を元にして非常に多数の辞典が編集?発行された。
- それによって基礎的な文字の習得を経て、初めて往来物などによる教科書を用いた教育が行われた。
- 『童子教』?『実語教』などが教科書として用いられたが、次第に往来物が教科書の中心となっていく。
- 寺子屋では往来物と称される教科書が使用されていて、『実語教』、『童子教』、『女大学』などがよく使われた。
- 江戸時代に入ると、『庭訓往来』のような既成の往来物に加えて新たな往来物が目的に応じて著されるようになった。
- 江戸時代に入ると、『庭訓往来』のような既成の往来物に加えて新たな往来物が目的に応じて著されるようになった。
- その後室町時代前期にかけて『貴嶺問答』?『雑筆往来』、そして中世往来物の代表作とされる『庭訓往来』が現れた。
- 用往来物造句挺难的,這是一个万能造句的方法
- 鎌倉時代には毎月2通分の往復書簡で季節感や行事を織り込んだ『十二月往来』が著され、後世の往来物の手本となった。
- 平安時代後期、藤原明衡が公家の文書作成のための参考とするために日本最古の往来物とされる『雲州消息』を執筆することとなる。
- 当時の武家社会の実情に即してかつ簡明ながらも生活に必要な実用的知識を網羅的に収録したこの本は江戸時代まで往来物の定番とされた。
- 庭訓往来(ていきんおうらい)とは、往来物(往復の手紙)の形式をとる、寺子屋で習字や読本として使用された初級の教科書の一つである。
- 江戸時代には教育熱の高まりとともに、寺子屋などで庶民が学ぶ往来物などの教科書でも御家流の書が用いられていたことから、爆発的に普及。
- この時代までの往来物は公家や僧侶などの知識人によって書かれる事が多く、こうした江戸時代以前の作品をまとめて「古往来(こおうらい)」と呼ぶ。
- 次に往来物の『桂川地蔵記』(応永23年10月14日条)に天国(刀工)以降、「鎌倉新藤五、彦四郎、五郎入道、九郎次郎???」と掲載されている。
- 『富士野往来』に始まる歴史物語を織り込んだものは「武家往来」とも呼ばれ、十返舎一九が伝記型の往来物を確立し、更に史詩型の往来物へと発展した。
- 『富士野往来』に始まる歴史物語を織り込んだものは「武家往来」とも呼ばれ、十返舎一九が伝記型の往来物を確立し、更に史詩型の往来物へと発展した。
- 往来物(おうらいもの)とは、平安時代後期より、明治時代初頭にかけて主に往復書簡などの手紙類の形式をとって作成された初等教育用の教科書の総称である。
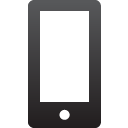 手机版
手机版